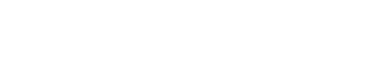2022.01.24
申立書は診断書に即することが大事
本人の症状を的確に表している診断書ですと申立書の内容も信憑性を増してきます。
医学的見地と実際の日常生活の融合により、より確信にふれることができるようになるからです。
症状を的確に表している診断書を医師に作成して頂くためには、普段の短い診察の中で医師とコミュニケーションがとれている必要があります。
診断書には、医師がご本人を理解していることが記載されます。
申立書は、日常生活・就労状況の困難さを記載していきます。
つまり、診断書で医学的に証明されたことを、申立書で実際の日常生活等ではどうなのかを証明していくのです。
だから、診断書だけ素晴らしくても、審理において足りないし、申立書だけ素晴らしくても、審理において足りません。
もちろん、診断書の内容が審理で弱いなら、そこを補填していき時には診断書と同等の証明をすることも必要となるのが申立書の役割です。
しかし、診断書の内容がしっかりとしているなら、申立書の内容は、そのしっかりとしている診断書の内容を押し上げることも可能になり得ます。
診断書に即した申立書は、審理において大きな武器になるのです。
だから、当事務所では、診断書は当たり前として申立書にも特に力を入れています。
医学的見地と実際の日常生活の融合により、より確信にふれることができるようになるからです。
症状を的確に表している診断書を医師に作成して頂くためには、普段の短い診察の中で医師とコミュニケーションがとれている必要があります。
診断書には、医師がご本人を理解していることが記載されます。
申立書は、日常生活・就労状況の困難さを記載していきます。
つまり、診断書で医学的に証明されたことを、申立書で実際の日常生活等ではどうなのかを証明していくのです。
だから、診断書だけ素晴らしくても、審理において足りないし、申立書だけ素晴らしくても、審理において足りません。
もちろん、診断書の内容が審理で弱いなら、そこを補填していき時には診断書と同等の証明をすることも必要となるのが申立書の役割です。
しかし、診断書の内容がしっかりとしているなら、申立書の内容は、そのしっかりとしている診断書の内容を押し上げることも可能になり得ます。
診断書に即した申立書は、審理において大きな武器になるのです。
だから、当事務所では、診断書は当たり前として申立書にも特に力を入れています。