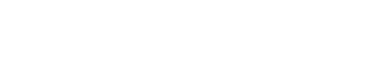2022.02.28
法定免除のメリットとリスク
障害年金の1級と2級に該当すると、「法定免除」が適用されます。
「法定免除」とは、「障害年金1級と2級」、「生活保護」などを受給している方が象で、国民年金保険料を法律として、免除してくれる制度です。
一見、このような制度ですと、「障害年金1級・2級」を受給すると、自動的に「法定免除」に切り替わるように思えます。
しかし、実際は、違います。
ご自身のお住まいの市役所で、「法定免除」の申請書を書き、そこで提出をして、はじめて「法定免除」が受理されます。
つまり、「法定免除」の届出を提出しないと、次年度も国民年金保険料の納付書が送られ、納付義務を負うことになります。
障害年金は終身年金ではないため、障害が治癒して障害年金を受給しない場合には老齢年金の対象になります。
法定免除の期間は0.5月納付として計算されるため、老齢年金の受給額が少なくなります。
そのため、免除を受けるのか保険料を支払うのかを選択することになります。
ご自身の生活状況や障害の状態により判断することが必要になります。
「法定免除」とは、「障害年金1級と2級」、「生活保護」などを受給している方が象で、国民年金保険料を法律として、免除してくれる制度です。
一見、このような制度ですと、「障害年金1級・2級」を受給すると、自動的に「法定免除」に切り替わるように思えます。
しかし、実際は、違います。
ご自身のお住まいの市役所で、「法定免除」の申請書を書き、そこで提出をして、はじめて「法定免除」が受理されます。
つまり、「法定免除」の届出を提出しないと、次年度も国民年金保険料の納付書が送られ、納付義務を負うことになります。
障害年金は終身年金ではないため、障害が治癒して障害年金を受給しない場合には老齢年金の対象になります。
法定免除の期間は0.5月納付として計算されるため、老齢年金の受給額が少なくなります。
そのため、免除を受けるのか保険料を支払うのかを選択することになります。
ご自身の生活状況や障害の状態により判断することが必要になります。