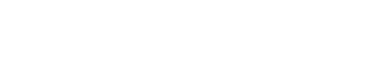2022.11.04
診断書の種類
診断書は、障害年金の申請において大事な書類です。
それだけに、きちんとご自身の障害状態が表せる診断書を使って欲しいです。
色々なホームぺージをみると、「この病気には、この診断書」というような表記があると思います。概ね、「この病気には、この診断書」という判断で申請をしても問題がないことが多いです。
しかし、“難病や病気から出ている症状だが、ホームページなどで表記されている診断書では、病状を表せない”ということが、しばしば出てきます。
もし、そのままご自身の障害状態を的確に表すことの出来ない診断書で申請をしたら、審査官に、ご自身の障害状態が伝わりにくくなりますから、その分だけ、認定確率は下がってしまいます。
病気による障害は、個人差があります。
その個人差までも出来る限り表すことが可能な、診断書を選ばないといけません。ですから、一概に「この病気では、この診断書」というような公式にも似た判断では、申請をしても、認定されないことが起こるのです。
それを無くす努力をするために、私は面談の時に、それら個人差による障害状態までも、見極め、最適な診断書を選び、認定確率を少しでも高くするようにしています。
大事な申請です。最善を尽くして、申請をさせて頂いております。
他者に伝える方法や制度の流れ等を明確にお応えします。
迷われたらとりあえず参加して下さい。
申請しようと考えたなら、行動に移すことをお勧めします。
障害年金を専門としている社会保険労務士がいます。
プロですから、あらゆる可能性を考え最善策を提示します。
「自分ではできない」とか「制度のことがイマイチわからない」など感じましたら、一度、ご相談ください。宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
依頼を受けた案件はベストを尽くした申請をして、依頼者の納得がいく申請ができるよう頑張っています。
不安を不安のままにして、申請に臨むのは心身的によくありません。
一人では乗り越えられない質問や不安を尋ねることができる。任せられるのであれば、その方が心身が少し楽になると思います。
もし、ご自身で申請を進めていて、少しでも不安を感じたなら、専門家に任せるのが認定を引き寄せる一番の近道になると思います。
それだけに、きちんとご自身の障害状態が表せる診断書を使って欲しいです。
色々なホームぺージをみると、「この病気には、この診断書」というような表記があると思います。概ね、「この病気には、この診断書」という判断で申請をしても問題がないことが多いです。
しかし、“難病や病気から出ている症状だが、ホームページなどで表記されている診断書では、病状を表せない”ということが、しばしば出てきます。
もし、そのままご自身の障害状態を的確に表すことの出来ない診断書で申請をしたら、審査官に、ご自身の障害状態が伝わりにくくなりますから、その分だけ、認定確率は下がってしまいます。
病気による障害は、個人差があります。
その個人差までも出来る限り表すことが可能な、診断書を選ばないといけません。ですから、一概に「この病気では、この診断書」というような公式にも似た判断では、申請をしても、認定されないことが起こるのです。
それを無くす努力をするために、私は面談の時に、それら個人差による障害状態までも、見極め、最適な診断書を選び、認定確率を少しでも高くするようにしています。
大事な申請です。最善を尽くして、申請をさせて頂いております。
他者に伝える方法や制度の流れ等を明確にお応えします。
迷われたらとりあえず参加して下さい。
申請しようと考えたなら、行動に移すことをお勧めします。
障害年金を専門としている社会保険労務士がいます。
プロですから、あらゆる可能性を考え最善策を提示します。
「自分ではできない」とか「制度のことがイマイチわからない」など感じましたら、一度、ご相談ください。宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
依頼を受けた案件はベストを尽くした申請をして、依頼者の納得がいく申請ができるよう頑張っています。
不安を不安のままにして、申請に臨むのは心身的によくありません。
一人では乗り越えられない質問や不安を尋ねることができる。任せられるのであれば、その方が心身が少し楽になると思います。
もし、ご自身で申請を進めていて、少しでも不安を感じたなら、専門家に任せるのが認定を引き寄せる一番の近道になると思います。