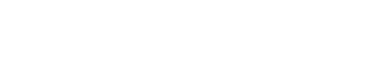2022.10.28
“審査請求”のススメ
障害年金の申請をし、診査の結果が「不支給(認定されず)」だった場合に、不服を申し立てるのが、“審査請求”です。
これとは別に、不服申し立て(審査請求)をしないで、再度、初診日証明書や診断書を取り直して、裁定請求をやり直すこともできます。
しかし、この場合の申請は、前の申請からそれほど経たずに申請をすることになります。
例え、最初の診断書(不支給になった診断書)で、ご自身の病状を正しく伝えきれていなかった。だから、再度 医師に正しく伝え直し、次回の診断書に反映させ、再度、ご自身の正しい病状の診断書で、裁定請求をし直したとしても
審査官の目がすれば、「最初の申請から数か月で、それほど診断書の内容が変わるものか?それほど病状が悪くなっているならば、入院なりの措置が取られていないとおかしい!?」と感じるのが普通だと思います。
審査官は、一日に、一ヶ月に、たくさんの申請書類を診査しているのですから、気付くはずです。ですから、最初の申請をしてから、最低でも約一年間は、次の裁定請求は控えた方が無難だと言えます。
とは言え、不支給の早い解決を望みたい気持ちも理解できます。
ですから、「審査請求」をするのです。
審査請求をし、診査から結果が出るまでの期間は、おおよそ5ヶ月~6ヶ月ほど掛ります。
最初の申請(裁定請求)をしてから、不支給の結果がでるまでに、約3ヶ月以上掛ったと思います。
裁定請求の申請から不支給の結果が出て(4ヶ月)、審査請求の申請から(審査請求の)結果がでる(6ヶ月)。つまり、裁定請求から審査請求の全期間で10ヶ月ほど掛ります。
これで、おおよそ一年間を費やしますが、この間も、不支給の結果の解決は進んでいます。
もし、この審査請求で不支給になったならば、その時、改めて裁定請求をしても良いと考えます
ただし、審査請求をする上で注意をしなければならないことが、“最初の診断書で、ご自身の症状・状態を伝えきれておらず、どう取っても「認定されない診断書」であれば、審査請求の結果を待つ期間の気持ちが辛いだけの時間になってしまうことです。”
診断書が「審査請求で認定されない可能性が高い診断書か、どうか」は、ご自身では解らないことが多いと思います。
解らないならば、一度、私に聞いて下さい。判断をさせて頂きます。
気持ちの浮き沈みを軽減させるためにも、ご自身の判断ではない、専門家の判断を頼りにしてみて下さい。宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
これとは別に、不服申し立て(審査請求)をしないで、再度、初診日証明書や診断書を取り直して、裁定請求をやり直すこともできます。
しかし、この場合の申請は、前の申請からそれほど経たずに申請をすることになります。
例え、最初の診断書(不支給になった診断書)で、ご自身の病状を正しく伝えきれていなかった。だから、再度 医師に正しく伝え直し、次回の診断書に反映させ、再度、ご自身の正しい病状の診断書で、裁定請求をし直したとしても
審査官の目がすれば、「最初の申請から数か月で、それほど診断書の内容が変わるものか?それほど病状が悪くなっているならば、入院なりの措置が取られていないとおかしい!?」と感じるのが普通だと思います。
審査官は、一日に、一ヶ月に、たくさんの申請書類を診査しているのですから、気付くはずです。ですから、最初の申請をしてから、最低でも約一年間は、次の裁定請求は控えた方が無難だと言えます。
とは言え、不支給の早い解決を望みたい気持ちも理解できます。
ですから、「審査請求」をするのです。
審査請求をし、診査から結果が出るまでの期間は、おおよそ5ヶ月~6ヶ月ほど掛ります。
最初の申請(裁定請求)をしてから、不支給の結果がでるまでに、約3ヶ月以上掛ったと思います。
裁定請求の申請から不支給の結果が出て(4ヶ月)、審査請求の申請から(審査請求の)結果がでる(6ヶ月)。つまり、裁定請求から審査請求の全期間で10ヶ月ほど掛ります。
これで、おおよそ一年間を費やしますが、この間も、不支給の結果の解決は進んでいます。
もし、この審査請求で不支給になったならば、その時、改めて裁定請求をしても良いと考えます
ただし、審査請求をする上で注意をしなければならないことが、“最初の診断書で、ご自身の症状・状態を伝えきれておらず、どう取っても「認定されない診断書」であれば、審査請求の結果を待つ期間の気持ちが辛いだけの時間になってしまうことです。”
診断書が「審査請求で認定されない可能性が高い診断書か、どうか」は、ご自身では解らないことが多いと思います。
解らないならば、一度、私に聞いて下さい。判断をさせて頂きます。
気持ちの浮き沈みを軽減させるためにも、ご自身の判断ではない、専門家の判断を頼りにしてみて下さい。宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。