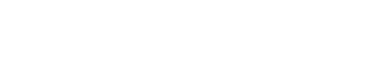2022.10.24
“診断書”と“申立書”の関係
障害年金申請には、医師しか書けない「診断書」と本人または代筆可能な「申立書」が必要です。
診断書は、普段の診察時に医師に伝えてある「症状・状態」以上の事は書かれないでしょう。
申立書は、診断書とは別に、請求人の「症状・状態」をご本人または代筆者が書き記すのですが、昨今は、以前よりもかなり診査の結果を左右する書類に変わってきたように思います。
診断書と整合性がとれていない申立書は、今も昔も、医師には診断書の内容について、ご本人または代筆者には、申立書に書いた内容の真偽を問う照会文が届くことがあり、ケース バイ ケースではありますが、それに答えなくてはなりません。
ですから、診断書の内容は、正確に読み取り、申立書を書く必要はあります。
それとは別に、診断書としては、認定されるべきなのに、何故か認定されていない申請があります。
特に、ご自身で申請をした場合に多くみられます。
これは、申立書に必要な情報を載せていないからなのです。
診断書に書かれている内容は、請求人の症状・状態を全て表していないものが多いです。
診断書のあの紙一枚の中に、請求人の症状・状態を全て表すことなど、かなり困難なことですから、だからと言って、診断書に一切書かれていない症状・状態を申立書に書いても、訴えを認めて貰う事は困難です。
ならば、何を書くのか!?
それは・・・「診断書に書かれた内容の詳細な症状・状態を書く」
これができれば、診査は、より認定に近づく可能性が高くなります。
つまり、“診断書”と“申立書”の関係は、同等な価値なのです。
以前は、「診断書さえ認定基準を満たしていれば、認定される。」などと言われた事もありましたが、今は違います。
申立書も診査の対象比率は高いのです。
今、認定される努力をするなら、医師の書く“診断書”の力だけでは足りなくなっています。
ご本人や代筆者が書く“申立書”の力が鍵になっています。
“診断書”と“申立書”の関係は、「50%+50%」に近づいてきているとも言えるのです。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
診断書は、普段の診察時に医師に伝えてある「症状・状態」以上の事は書かれないでしょう。
申立書は、診断書とは別に、請求人の「症状・状態」をご本人または代筆者が書き記すのですが、昨今は、以前よりもかなり診査の結果を左右する書類に変わってきたように思います。
診断書と整合性がとれていない申立書は、今も昔も、医師には診断書の内容について、ご本人または代筆者には、申立書に書いた内容の真偽を問う照会文が届くことがあり、ケース バイ ケースではありますが、それに答えなくてはなりません。
ですから、診断書の内容は、正確に読み取り、申立書を書く必要はあります。
それとは別に、診断書としては、認定されるべきなのに、何故か認定されていない申請があります。
特に、ご自身で申請をした場合に多くみられます。
これは、申立書に必要な情報を載せていないからなのです。
診断書に書かれている内容は、請求人の症状・状態を全て表していないものが多いです。
診断書のあの紙一枚の中に、請求人の症状・状態を全て表すことなど、かなり困難なことですから、だからと言って、診断書に一切書かれていない症状・状態を申立書に書いても、訴えを認めて貰う事は困難です。
ならば、何を書くのか!?
それは・・・「診断書に書かれた内容の詳細な症状・状態を書く」
これができれば、診査は、より認定に近づく可能性が高くなります。
つまり、“診断書”と“申立書”の関係は、同等な価値なのです。
以前は、「診断書さえ認定基準を満たしていれば、認定される。」などと言われた事もありましたが、今は違います。
申立書も診査の対象比率は高いのです。
今、認定される努力をするなら、医師の書く“診断書”の力だけでは足りなくなっています。
ご本人や代筆者が書く“申立書”の力が鍵になっています。
“診断書”と“申立書”の関係は、「50%+50%」に近づいてきているとも言えるのです。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。