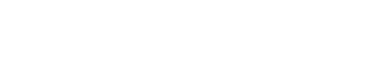2022.02.07
公的年金と私的年金
老後2000万円が必要だとして年金制度に不安を持っている人が多いと思います。年金の財源も、ますます厳しくなっていることはご存じのとおりです。
国は年金制度の安定化に向けた対策として保険料を上げ、また給付については経済状態によってスライドさせたり、厚生年金保険加入条件を変更したり、様々な対策を進めています。
年金制度の将来については不安視する人が多いと思います。「いずれ年金は破たんする。自分は年金に頼らない。自分で貯める。」などという方がいらっしゃいますが、それで本当に大丈夫でしょうか。膨大な財産をお持ちの方はそれでいいと思います。しかし、ごく普通の方にとって支給される年金は、額の多少にかかわらず、「抜群に優れた保険」だと思います。
そこで、「公的年金」と「私的年金」を比較して日本の年金制度がいかに有利な保険なのかを説明します。
「公的年金」とは主に国民年金と厚生年金保険をいいます。
「私的年金」とは、生命保険の養老年金や各種金融機関の商品などのことです。
(1)全額所得控除の対象
「公的年金」は課税所得から全額控除されます。そのために所得税や住民税が軽減されます。
「私的年金」では控除は一部だけです。
(2)物価スライド
「公的年金」は実質価値を維持する金額を支給されます。つまり物価が上がれば、原則、国が年金の実質価値を維持することを保障します。
「私的年金」では、物価が大きく上がってしまった場合には年金の実質価値を維持することは困難です。
(3)終身保障
「公的年金」は支払った保険料に関係なく、一生、亡くなるまで給付される終身年金です。財源は、本人や後世代の支払った保険料と運用収入だけでなく、国庫負担(税金からの補てん)も小さくありません。保険を運用するための事務費は国庫負担(税金負担)で行われ給付費は確保されます。
「私的年金」では、支払った保険料の資金が底をつけば終わる有期年金が中心です。人間の寿命は分かりませんから有期では不安です。
(4)補償の範囲
「公的年金」は、老後(老齢年金)だけでなく、万が一、障害者になってしまった場合(障害年金)や一家の生計を支えていた方が死亡してしまった場合(遺族年金)もカバーします。
「公的年金」は老後の「所得補償の柱」と位置付けられ、「私的年金」は、「より豊かな老後生活を支える」ためのものです。
「公的年金」は国が保障します。万が一「公的年金」が破たんすることがあるなら、日本の財政も破たんしていることが想定されます。
その場合には、保険会社や金融機関も正常な経営状態であることは難しく日本自体が破たんしてしまいます。その時には自分の財産の確保すらできなくなります。
現在の「公的年金」を直視して、適正に立て直していくことが重要なことだと思います。少子高齢化は事実なので、年金財源を確保し、給付の配分を見直し、年金制度が若い世代まで続けられる仕組みにしていく必要があると思います。
国は年金制度の安定化に向けた対策として保険料を上げ、また給付については経済状態によってスライドさせたり、厚生年金保険加入条件を変更したり、様々な対策を進めています。
年金制度の将来については不安視する人が多いと思います。「いずれ年金は破たんする。自分は年金に頼らない。自分で貯める。」などという方がいらっしゃいますが、それで本当に大丈夫でしょうか。膨大な財産をお持ちの方はそれでいいと思います。しかし、ごく普通の方にとって支給される年金は、額の多少にかかわらず、「抜群に優れた保険」だと思います。
そこで、「公的年金」と「私的年金」を比較して日本の年金制度がいかに有利な保険なのかを説明します。
「公的年金」とは主に国民年金と厚生年金保険をいいます。
「私的年金」とは、生命保険の養老年金や各種金融機関の商品などのことです。
(1)全額所得控除の対象
「公的年金」は課税所得から全額控除されます。そのために所得税や住民税が軽減されます。
「私的年金」では控除は一部だけです。
(2)物価スライド
「公的年金」は実質価値を維持する金額を支給されます。つまり物価が上がれば、原則、国が年金の実質価値を維持することを保障します。
「私的年金」では、物価が大きく上がってしまった場合には年金の実質価値を維持することは困難です。
(3)終身保障
「公的年金」は支払った保険料に関係なく、一生、亡くなるまで給付される終身年金です。財源は、本人や後世代の支払った保険料と運用収入だけでなく、国庫負担(税金からの補てん)も小さくありません。保険を運用するための事務費は国庫負担(税金負担)で行われ給付費は確保されます。
「私的年金」では、支払った保険料の資金が底をつけば終わる有期年金が中心です。人間の寿命は分かりませんから有期では不安です。
(4)補償の範囲
「公的年金」は、老後(老齢年金)だけでなく、万が一、障害者になってしまった場合(障害年金)や一家の生計を支えていた方が死亡してしまった場合(遺族年金)もカバーします。
「公的年金」は老後の「所得補償の柱」と位置付けられ、「私的年金」は、「より豊かな老後生活を支える」ためのものです。
「公的年金」は国が保障します。万が一「公的年金」が破たんすることがあるなら、日本の財政も破たんしていることが想定されます。
その場合には、保険会社や金融機関も正常な経営状態であることは難しく日本自体が破たんしてしまいます。その時には自分の財産の確保すらできなくなります。
現在の「公的年金」を直視して、適正に立て直していくことが重要なことだと思います。少子高齢化は事実なので、年金財源を確保し、給付の配分を見直し、年金制度が若い世代まで続けられる仕組みにしていく必要があると思います。