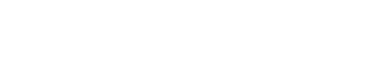2023.01.09
肢体(身体障害者)の診断書
「交通事故の後遺症」や「脳梗塞・脳出血の後遺症」「膠原病」などで、手足が不自由で日常生活が困難。または、体を支えることが困難。
このような方は、障害年金の申請をするときに、「肢体の診断書」を使うことが一般的です。
この診断書は「首・肩・手足・腰の関節の可動域と筋力」などを医師又は療法士等が検査し、診断書の中に記載していきます。
この検査で、「各関節可動域」を考えて「握力の強さ」や「服の着脱がどの程度できるか」、「どの程度なら立ち上がれるか。または、立ち上がれないか。」、「どの程度、階段の昇降ができるか。または、できないか。」など日常生活のなかの不自由さの程度も診断書の中に記載されていきます。
ここで問題なるのが、「各関節可動域や筋力」と「日常生活の不自由さ」の整合性です。
「股関節がここまで動くのに、立てない」となっている診断書。
「手に筋力があるのに、握力がない」となっている診断書。
「体が支えられるのに、寝たきりに近い」となっている診断書。
など、整合性が合わない診断書は、審査されるときに、審査官に疑われてしまいます。
結果、不支給になることもあります。
普段から動かしている「関節可動域と筋力」を検査し、「日常生活の不自由さ」も記載してもらえば、整合性のとれた診断書になり易いと思います。
その診断書をもって、ご自身の日常生活状況を「病歴・就労状況等申立書」に書き、審査に臨まれることをお勧めします。
「関節可動域や筋力」が乏しいから認定される側面はあると思います。
しかし、それは「関節可動域や筋力」と「日常生活の不自由さ」をみた時に、整合性のとれた診断書あっての話です。
審査官は、たくさんの診断書をみています。
ですから、逆に整合性がとれない箇所があれば、琴線に引っかかって分かってしまうのだと思います。
迷うことがあれば、よかったら ご相談下さい。
診断書は、医学的な知識も必要ですし、それを申立書の中で表現するには、コツが必要です。
ここが社労士の出番になります。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。
このような方は、障害年金の申請をするときに、「肢体の診断書」を使うことが一般的です。
この診断書は「首・肩・手足・腰の関節の可動域と筋力」などを医師又は療法士等が検査し、診断書の中に記載していきます。
この検査で、「各関節可動域」を考えて「握力の強さ」や「服の着脱がどの程度できるか」、「どの程度なら立ち上がれるか。または、立ち上がれないか。」、「どの程度、階段の昇降ができるか。または、できないか。」など日常生活のなかの不自由さの程度も診断書の中に記載されていきます。
ここで問題なるのが、「各関節可動域や筋力」と「日常生活の不自由さ」の整合性です。
「股関節がここまで動くのに、立てない」となっている診断書。
「手に筋力があるのに、握力がない」となっている診断書。
「体が支えられるのに、寝たきりに近い」となっている診断書。
など、整合性が合わない診断書は、審査されるときに、審査官に疑われてしまいます。
結果、不支給になることもあります。
普段から動かしている「関節可動域と筋力」を検査し、「日常生活の不自由さ」も記載してもらえば、整合性のとれた診断書になり易いと思います。
その診断書をもって、ご自身の日常生活状況を「病歴・就労状況等申立書」に書き、審査に臨まれることをお勧めします。
「関節可動域や筋力」が乏しいから認定される側面はあると思います。
しかし、それは「関節可動域や筋力」と「日常生活の不自由さ」をみた時に、整合性のとれた診断書あっての話です。
審査官は、たくさんの診断書をみています。
ですから、逆に整合性がとれない箇所があれば、琴線に引っかかって分かってしまうのだと思います。
迷うことがあれば、よかったら ご相談下さい。
診断書は、医学的な知識も必要ですし、それを申立書の中で表現するには、コツが必要です。
ここが社労士の出番になります。
宝塚市や西宮市などの阪神間及び兵庫県をメインに、ご相談を随時受け付けています。